2024年06月27日
イェルサレム第3神殿として建立された【伊勢神宮】!
★【追記】~何故「雄略天皇21年」(幻の西暦477年=ユダヤ創世記暦4418年)を伊勢皇大神宮(内宮)の建立年と定義し、設定されたのか。つまりそれは、西暦1年.辛酉(神武天皇即位元年に始まる皇暦1年=創世記暦3941年+AD477年=4418-180=創世記暦4238年がユダヤ暦)よりユダヤ暦は180年少なかった。それで、先ず『ホツマツタヱ』(日本人の聖書に当る)文書を用い、皇暦年(天鈴暦は790年で終焉)を暫定的に設定するを以て、その誤差の180年を解消(景行天皇即位元年はエルサレム第二神殿陥落の翌年に当る幻の西暦71年)させました。そして、景行天皇崩御後の文書(成務天皇~仁徳天皇時頃迄)は、武内宿禰(ホツマ28章/或る文お、代々に伝ふる、武内は、遂に永らふ、道となるかな)に委ねられた事によって、雄略天皇21年、即ち「AD477年+180=皇暦657年は垂仁天皇26年」(垂仁26年は伊勢神宮建立年としてホツマに記載済み)の時として、皇大神宮の禰宜(ネギ/宮司の補佐)だった荒木田氏一族の手で文書が書き残され、それが『太神宮諸雑事記第一』として現在に残されています!
…
★~伊勢神宮の建立年に付いては、我が国最古の歴史書とされる『日本書紀』を始めとして、どの歴史書にも全く、記載されていません。然し、伊勢神宮の境内には伊勢神宮の建立年の事が記された掲示板が設置されています。つまりそれは、皇大神宮(内宮)禰宜の荒木田一族の手で書き継がれ、平安末期迄の主要事項を編年体で記された文書として、その最初に当る【太神宮諸雑事記・第一】に記載(紀元前7年に当る長髄彦討伐開始年から「484」年目の雄略天皇21年の時とする)されています。尚、景行天皇の即位年は、イェルサレム第2神殿陥落の翌年に当る「AD71年」(景行天皇28年は唐の章和帝12年/正確には後漢の和帝章和元年=AD87年+和帝12年=AD満97年-景行28=AD71年と成る)として設定されています。因みに、数価「484」とは、ヘブル文字22×22=484に当り、その数価はカバラのゲマトリア教義では最も重要な数価とされています。
…
神社の置き千木の形状は、ギリシアのイオニア式文字配列第22番目(χi)の「χ」(数価千を言い表す文字/単位キロの語元文字)が元形でした。その意味する処は「完成」(千は10の3乗で完璧さの極致の意)。つまり、我がヤマトの国とは完成された国として創建されました。因みに、古来の民家等の屋根には屋根が風に飛ばされないよう押さえている長い木製形状をチギと言うのは間違いです。つまり、倭語チギ(漢字は千木)としての定義付けは民家ではなく、ムロヤ(高床の倉庫様式)の屋根にχi文字形状を単体で設置するを以て、初めて「チギ=千木」と称し、その全体的構造(建物の中は空洞とする)に対し、ヤシロ(社)と定義付けられました。そしてその命名者は初代大物主(クシキネ=事代主)として秀真伝(21章・室屋造りて民を生む、後ヤ手結びヤシロ成る~)に記述されています。
…
では何故、倭語で「チギ」と命名されたかと言えば、それは【死海文書】(1947年にクムラン洞穴から発見)に書かれていた文言に起因します。つまりそれは、紀元前に聖書を写本するに当たりGodヤハウェの御名の部分は後でヘブル文字(YHVHの角文字)を記入する為、空白的に開けていて、その代わりに角文字に似たギリシア文字の「π・i」(後年の訳者は間違ってピィ・ピィと発音していた)の字を仮に当てていました。そのギリシア文字「π」に当る第16番目の字配列に対し我が国で造語するにあっては、母音アイウエオ(ギリシアの母音アエイオウの並べかえ)に対し、数秘術(ゲマトリア)を駆使する必要から、ホツマ文字を【ア・ワ】(天・地)の歌(アカハナマ~)の順に並べ変えれば、その第16番目に倭語「チ」に当ります。従って、その文字の呼称である倭語「チ」に対し倭語数価1000=千を意味表す文字として設定し、「チギ」と言う単語として造語されたのでした!
…
因みに、伊勢神宮様式の千木の形状は見て字の如く、それはホツマ文字の【チ】(冂字形+アルファベットY字形)の形状文字と、【キ】(冂+アルファベットI字形)形状文字との合字を用いての造語(単語)であり、従って、その字の如く「チ(π)キ(木)」と呼ばれています。又、別称としては「角刺千木」とも称されている。
…

…

…
★~伊勢神宮の建立年に付いては、我が国最古の歴史書とされる『日本書紀』を始めとして、どの歴史書にも全く、記載されていません。然し、伊勢神宮の境内には伊勢神宮の建立年の事が記された掲示板が設置されています。つまりそれは、皇大神宮(内宮)禰宜の荒木田一族の手で書き継がれ、平安末期迄の主要事項を編年体で記された文書として、その最初に当る【太神宮諸雑事記・第一】に記載(紀元前7年に当る長髄彦討伐開始年から「484」年目の雄略天皇21年の時とする)されています。尚、景行天皇の即位年は、イェルサレム第2神殿陥落の翌年に当る「AD71年」(景行天皇28年は唐の章和帝12年/正確には後漢の和帝章和元年=AD87年+和帝12年=AD満97年-景行28=AD71年と成る)として設定されています。因みに、数価「484」とは、ヘブル文字22×22=484に当り、その数価はカバラのゲマトリア教義では最も重要な数価とされています。
…
神社の置き千木の形状は、ギリシアのイオニア式文字配列第22番目(χi)の「χ」(数価千を言い表す文字/単位キロの語元文字)が元形でした。その意味する処は「完成」(千は10の3乗で完璧さの極致の意)。つまり、我がヤマトの国とは完成された国として創建されました。因みに、古来の民家等の屋根には屋根が風に飛ばされないよう押さえている長い木製形状をチギと言うのは間違いです。つまり、倭語チギ(漢字は千木)としての定義付けは民家ではなく、ムロヤ(高床の倉庫様式)の屋根にχi文字形状を単体で設置するを以て、初めて「チギ=千木」と称し、その全体的構造(建物の中は空洞とする)に対し、ヤシロ(社)と定義付けられました。そしてその命名者は初代大物主(クシキネ=事代主)として秀真伝(21章・室屋造りて民を生む、後ヤ手結びヤシロ成る~)に記述されています。
…
では何故、倭語で「チギ」と命名されたかと言えば、それは【死海文書】(1947年にクムラン洞穴から発見)に書かれていた文言に起因します。つまりそれは、紀元前に聖書を写本するに当たりGodヤハウェの御名の部分は後でヘブル文字(YHVHの角文字)を記入する為、空白的に開けていて、その代わりに角文字に似たギリシア文字の「π・i」(後年の訳者は間違ってピィ・ピィと発音していた)の字を仮に当てていました。そのギリシア文字「π」に当る第16番目の字配列に対し我が国で造語するにあっては、母音アイウエオ(ギリシアの母音アエイオウの並べかえ)に対し、数秘術(ゲマトリア)を駆使する必要から、ホツマ文字を【ア・ワ】(天・地)の歌(アカハナマ~)の順に並べ変えれば、その第16番目に倭語「チ」に当ります。従って、その文字の呼称である倭語「チ」に対し倭語数価1000=千を意味表す文字として設定し、「チギ」と言う単語として造語されたのでした!
…
因みに、伊勢神宮様式の千木の形状は見て字の如く、それはホツマ文字の【チ】(冂字形+アルファベットY字形)の形状文字と、【キ】(冂+アルファベットI字形)形状文字との合字を用いての造語(単語)であり、従って、その字の如く「チ(π)キ(木)」と呼ばれています。又、別称としては「角刺千木」とも称されている。
…

…

2024年06月01日
今迄「誰にも言わなかった事」(41歳/今から36年前の話)!
(◆「ハマボウの花の花の下で」より ~ https://erusaremu4654.jugem.jp/?eid=2 )。
…
昭和63=1988年1月18日(月曜)の朝6時に目覚まし時計で目を覚ますが、後1時間程寝る事とする。と、その時~突然「見つかったか!」と、ドスの効いた低い男の声がした(一瞬ドキッとする/自分一人の部屋に人の声がして驚いた)。ので目を開けようとするが目が開かない。体も自由に成らず、もがくと手が動いたので指で唇を摘んで口を動かしながら「誰や!」と叫ぶが声にならず、段々息苦しくなってきた。それで力任せに大きな声を出したら「パッ」と部屋(四畳半)が明るくなり目が開き見えるようになる。然し、良く見ると部屋は自分の部屋だが、テレビの位置にテレビが無く、その壁の下の部分に声の主の男の顔(角があれば般若の面的な顔)が張り付いていて、ニヤリと笑った。それを見て、「自分は夢の中の世界に居る」と言う事をハッキリ自覚する。然しそれは久しぶりの「夢の世界」(幽体離脱し異次元を体験す)であった。
…
それで、声の主の男の顔に対し私は~「自分の将来はどうなるかを教えてほしい」と言うと、角が無い般若的な顔の形が崩れ、白い犬に変身し壁から抜け出した。噛まれると思い体を動かそうとするが未だ体が動かないので動く手で噛まれないよう白い犬の頭を撫でようとすると犬が私の顔をペロリと舐めた。その時、隣の部屋(六畳間)の襖と柱の間から何か光っているのが少し見えたので其処へ行こうと思ったら体が動いたので隣の六畳間に行く。すると、南側の壁に際に【祭壇】(祭壇の回りは小さな星のような物がキラキラ光っていて祭壇全体は金色に輝いていた)が設えてあり、巫女さんような一人の女性が白い着物を着て祭壇に向かって坐っていた。それて「自分の将来を占って」と頼むと、こちらを向いて引き受けてくれた。そして、私に背を向け祭壇に向かって祈り出したので私も二礼二拍一礼(神道の基本儀式)し、祈る真似事をする。女性は暫く祈って私のほうを向いて「貴方の将来は良くない」と言う信託であった。それでもう一度占ってほしいと頼むと、女性が言うには「20年間・強盗スリを担当するが一度も間違いは無い」と言う。そしてその原因は「ウラコロビ」があるからだと言い、とりあってくれなかった。それで、元の四畳半の部屋に行くと、白い犬は一人の着物を着た女性に変わっていた。それでその女性に何か話かけようとするとした瞬間、二人は或る山路に立っていた。そしてその女性が言うには、此の先に知っている家があると言うので行こうとすると、何時の間にか或教室に立っていた。そして其処には数人の生徒が居たが私と女性には無関心であった。それで白い犬が変身した女性に対し私は質問した。つまり、「神武天皇の即位年は何年か?」と訊くと~女性が言うには「22と44の間」(22×44÷2=484)と答えた。それを忘れないように教室の黒板にチョークで「22」と「44」と書こうとするが数字にならなず、書いた後から直ぐ消えていく。そしてチョークも水となって床に落ちた。従って、その状況自体が「夢の世界である事」と再認識し、以て、その夢の世界を探索する事とする。それでその教室を一人で玄関に出ると、其処は大きなホテルのようだったが誰もいない。外は真夏の朝のようで、明るい太陽光線で目が痛かった。自分が出て来た建物の回りを見ると周りも大きなビルばかり建っていて、それらのビルから沢山の人がゾロゾロ出て来た。そして私が出て来たビルの前に集まり、全員が体操を始めた。それで、その集団を掻き分けるようにして抜け出し当てもなくさ迷った後、何時しか目が覚めた。
…
後で考えたら~闇の中からの声「見つかったか!」とは、その3年前(昭和60年=1985年)に「神武天皇の即位元年」設定方式の謎に取り組んでいた事に起因し、その翌年、2つの「予言」(未来の予測/預言の意ではない)的な正夢を見る。その話(死後の世界を覗いた話&幽体離脱)は次のブログに書く事と致します~。
…

…
昭和63=1988年1月18日(月曜)の朝6時に目覚まし時計で目を覚ますが、後1時間程寝る事とする。と、その時~突然「見つかったか!」と、ドスの効いた低い男の声がした(一瞬ドキッとする/自分一人の部屋に人の声がして驚いた)。ので目を開けようとするが目が開かない。体も自由に成らず、もがくと手が動いたので指で唇を摘んで口を動かしながら「誰や!」と叫ぶが声にならず、段々息苦しくなってきた。それで力任せに大きな声を出したら「パッ」と部屋(四畳半)が明るくなり目が開き見えるようになる。然し、良く見ると部屋は自分の部屋だが、テレビの位置にテレビが無く、その壁の下の部分に声の主の男の顔(角があれば般若の面的な顔)が張り付いていて、ニヤリと笑った。それを見て、「自分は夢の中の世界に居る」と言う事をハッキリ自覚する。然しそれは久しぶりの「夢の世界」(幽体離脱し異次元を体験す)であった。
…
それで、声の主の男の顔に対し私は~「自分の将来はどうなるかを教えてほしい」と言うと、角が無い般若的な顔の形が崩れ、白い犬に変身し壁から抜け出した。噛まれると思い体を動かそうとするが未だ体が動かないので動く手で噛まれないよう白い犬の頭を撫でようとすると犬が私の顔をペロリと舐めた。その時、隣の部屋(六畳間)の襖と柱の間から何か光っているのが少し見えたので其処へ行こうと思ったら体が動いたので隣の六畳間に行く。すると、南側の壁に際に【祭壇】(祭壇の回りは小さな星のような物がキラキラ光っていて祭壇全体は金色に輝いていた)が設えてあり、巫女さんような一人の女性が白い着物を着て祭壇に向かって坐っていた。それて「自分の将来を占って」と頼むと、こちらを向いて引き受けてくれた。そして、私に背を向け祭壇に向かって祈り出したので私も二礼二拍一礼(神道の基本儀式)し、祈る真似事をする。女性は暫く祈って私のほうを向いて「貴方の将来は良くない」と言う信託であった。それでもう一度占ってほしいと頼むと、女性が言うには「20年間・強盗スリを担当するが一度も間違いは無い」と言う。そしてその原因は「ウラコロビ」があるからだと言い、とりあってくれなかった。それで、元の四畳半の部屋に行くと、白い犬は一人の着物を着た女性に変わっていた。それでその女性に何か話かけようとするとした瞬間、二人は或る山路に立っていた。そしてその女性が言うには、此の先に知っている家があると言うので行こうとすると、何時の間にか或教室に立っていた。そして其処には数人の生徒が居たが私と女性には無関心であった。それで白い犬が変身した女性に対し私は質問した。つまり、「神武天皇の即位年は何年か?」と訊くと~女性が言うには「22と44の間」(22×44÷2=484)と答えた。それを忘れないように教室の黒板にチョークで「22」と「44」と書こうとするが数字にならなず、書いた後から直ぐ消えていく。そしてチョークも水となって床に落ちた。従って、その状況自体が「夢の世界である事」と再認識し、以て、その夢の世界を探索する事とする。それでその教室を一人で玄関に出ると、其処は大きなホテルのようだったが誰もいない。外は真夏の朝のようで、明るい太陽光線で目が痛かった。自分が出て来た建物の回りを見ると周りも大きなビルばかり建っていて、それらのビルから沢山の人がゾロゾロ出て来た。そして私が出て来たビルの前に集まり、全員が体操を始めた。それで、その集団を掻き分けるようにして抜け出し当てもなくさ迷った後、何時しか目が覚めた。
…
後で考えたら~闇の中からの声「見つかったか!」とは、その3年前(昭和60年=1985年)に「神武天皇の即位元年」設定方式の謎に取り組んでいた事に起因し、その翌年、2つの「予言」(未来の予測/預言の意ではない)的な正夢を見る。その話(死後の世界を覗いた話&幽体離脱)は次のブログに書く事と致します~。
…

2024年05月14日
【松浦】(松浦郡)の語元~
「松浦の語元」について~
…
※我が国の水軍の王だった【松の君】とは、「松の瘤的筋肉隆々・八十チカラの持ち主」(ミマキイリヒコ=崇神天皇の時代)の意が語元だった。そしてその王が居住地としていたのは我が国が世界に向けた表玄関とする伊万里(ゐまり/ゲマトリア358は創世記49・9~10に記す預言文言数価)を含む「マツラ」(魏志倭人伝に記す末廬国/現在に言う松浦)であった。因みに末羅の「末」は「松」が正しい。
…
その【松の君】の水軍を祖とする住吉のルーツは、いにしえの「①ツキスミ・島津ウシ」(呉の会稽から渡海し住み着いた地に対しツキスミと言う)に始まり→「②オキツ彦・③?・④シガ彦・⑤安曇・⑥オキツトリのウ・⑦カナサキ住吉の翁・⑧ハデ祇」(孫の豊玉姫は貴船のムツ船魂/彦ホホデミ尊の后)とされていすます。そして、天皇系譜としては、豊玉姫の嫡子・鸕鷀草葺不合尊」(ウガヤフキアエズノミコト)を経て、「神武天皇」へと繋げられています。
…
◆「木起し神社」(牧島地区/佐賀県伊万里市木須町木須西に建立/神功皇后が朝鮮半島からの帰還地)。その【木起神社】の由来に付いては★『伊万里市史』(民俗・生活・宗教 編)の「545ページ」に記載されています…!
…
★前文略~この木起こし参道には昔から何本かの松の大木が生えとって、参道の脇の田んなかの方へ、ベターっと横になって這(ホ)うとったてたい。その田んなかば作りよる村の者は、「邪魔になる松の木ばい。田んなかには、影んでくっし、かがまんば(屈む)田の草取りもされん。腰の痛うしてたまらんばい」て、いつでも愚痴ば、こぼしよらしたてたい。或る日の事、村の者達は集まって、「いっその事、松の木ば切ってしまおうか」て、話し合わしたちゅうたい。其処に、まだ村に留まっとんさった皇后(神功皇后)さんの来ごさって村の者から困っとる事ば聞かしたちゅう。そうして皇后さんは松の木に、「なおれ!」て、太うか声ばかけらしたちゅうたい。村の者達は、何の事か解らず、家に帰っていかしたちゅうたい。ところが、その晩の真夜中ごろたい。神社の方から、ものすごか物音の聞こえてきたてたい。「あの音は何じゃろか。大風じゃろか」て思いながら、誰でも夜の明くっとば、心配して待っとったちゅうたい。あくる日、村の者達が参道に行たてみて、うったまがらしたちゅう。「こりゃなんや。松の木のしっきゃあ、しゃーんて起きてしもうとっ!」何んと一晩の内に、地べたば、腹ぼうとった松の木のぜーんぶ天に向かって、立っとじゃなかね。村の者達は、「こりゃどがんなっとっとじゃろか。やっぱり皇后さんのおかげばい」て、感謝したちゅうたい。松の木が一晩で真直ぐ成ったけん、それからこっち、神社の名前ば、【木起神社】(キオコシ神社)て言う事になったてたい(後文略す)。
…
その「松の木起し」の語意は、神功皇后紀(『日本書紀』)に記す文言(神功皇后の新羅征伐)に関連します。その始まりは、倭の王=崇神天皇が任那の王に贈った土産を新羅が掠め取った事に起因(ホツマ文書のミマキイリヒコの58年条=34章・任那の王に贈った土産を新羅が掠め取った事に起因~それは『日本書紀』垂仁天皇即位当年の事として記載在り/その元典はホツマツタヱ文書34章のミマキの代・任那のアヤ)します。従って、倭の水軍が新羅に攻め入る時、~《神功皇后9年秋・時皇后親執斧鉞、令三軍曰、金鼓無節・旌旗錯亂、則士卒不整》とある。つまり、「カネツヅミ、ワイタメなし」。その意味は、「鐘を鳴らしても節度が無くなり、旗が錯乱したら戦の人、即ち、松の君(松浦水軍を率いた王の呼称)が率いる水軍どもの士気が整わない意」(戦を前にして士気をたかめろと言う叱咤文言)を示唆する文言に関連します。因みに、【松の君】(松の瘤的筋肉隆々・八十チカラの持ち主)が松浦郡の語元であり、後年の「住吉水軍」の祖となった人物でした!
…
その【松の君】の水軍(神功皇后の軍隊が新羅討伐から帰還した地に建立された神社/現在の建立地は移転後の場所)が、後に【木起神社】と言う~!
…


…
※我が国の水軍の王だった【松の君】とは、「松の瘤的筋肉隆々・八十チカラの持ち主」(ミマキイリヒコ=崇神天皇の時代)の意が語元だった。そしてその王が居住地としていたのは我が国が世界に向けた表玄関とする伊万里(ゐまり/ゲマトリア358は創世記49・9~10に記す預言文言数価)を含む「マツラ」(魏志倭人伝に記す末廬国/現在に言う松浦)であった。因みに末羅の「末」は「松」が正しい。
…
その【松の君】の水軍を祖とする住吉のルーツは、いにしえの「①ツキスミ・島津ウシ」(呉の会稽から渡海し住み着いた地に対しツキスミと言う)に始まり→「②オキツ彦・③?・④シガ彦・⑤安曇・⑥オキツトリのウ・⑦カナサキ住吉の翁・⑧ハデ祇」(孫の豊玉姫は貴船のムツ船魂/彦ホホデミ尊の后)とされていすます。そして、天皇系譜としては、豊玉姫の嫡子・鸕鷀草葺不合尊」(ウガヤフキアエズノミコト)を経て、「神武天皇」へと繋げられています。
…
◆「木起し神社」(牧島地区/佐賀県伊万里市木須町木須西に建立/神功皇后が朝鮮半島からの帰還地)。その【木起神社】の由来に付いては★『伊万里市史』(民俗・生活・宗教 編)の「545ページ」に記載されています…!
…
★前文略~この木起こし参道には昔から何本かの松の大木が生えとって、参道の脇の田んなかの方へ、ベターっと横になって這(ホ)うとったてたい。その田んなかば作りよる村の者は、「邪魔になる松の木ばい。田んなかには、影んでくっし、かがまんば(屈む)田の草取りもされん。腰の痛うしてたまらんばい」て、いつでも愚痴ば、こぼしよらしたてたい。或る日の事、村の者達は集まって、「いっその事、松の木ば切ってしまおうか」て、話し合わしたちゅうたい。其処に、まだ村に留まっとんさった皇后(神功皇后)さんの来ごさって村の者から困っとる事ば聞かしたちゅう。そうして皇后さんは松の木に、「なおれ!」て、太うか声ばかけらしたちゅうたい。村の者達は、何の事か解らず、家に帰っていかしたちゅうたい。ところが、その晩の真夜中ごろたい。神社の方から、ものすごか物音の聞こえてきたてたい。「あの音は何じゃろか。大風じゃろか」て思いながら、誰でも夜の明くっとば、心配して待っとったちゅうたい。あくる日、村の者達が参道に行たてみて、うったまがらしたちゅう。「こりゃなんや。松の木のしっきゃあ、しゃーんて起きてしもうとっ!」何んと一晩の内に、地べたば、腹ぼうとった松の木のぜーんぶ天に向かって、立っとじゃなかね。村の者達は、「こりゃどがんなっとっとじゃろか。やっぱり皇后さんのおかげばい」て、感謝したちゅうたい。松の木が一晩で真直ぐ成ったけん、それからこっち、神社の名前ば、【木起神社】(キオコシ神社)て言う事になったてたい(後文略す)。
…
その「松の木起し」の語意は、神功皇后紀(『日本書紀』)に記す文言(神功皇后の新羅征伐)に関連します。その始まりは、倭の王=崇神天皇が任那の王に贈った土産を新羅が掠め取った事に起因(ホツマ文書のミマキイリヒコの58年条=34章・任那の王に贈った土産を新羅が掠め取った事に起因~それは『日本書紀』垂仁天皇即位当年の事として記載在り/その元典はホツマツタヱ文書34章のミマキの代・任那のアヤ)します。従って、倭の水軍が新羅に攻め入る時、~《神功皇后9年秋・時皇后親執斧鉞、令三軍曰、金鼓無節・旌旗錯亂、則士卒不整》とある。つまり、「カネツヅミ、ワイタメなし」。その意味は、「鐘を鳴らしても節度が無くなり、旗が錯乱したら戦の人、即ち、松の君(松浦水軍を率いた王の呼称)が率いる水軍どもの士気が整わない意」(戦を前にして士気をたかめろと言う叱咤文言)を示唆する文言に関連します。因みに、【松の君】(松の瘤的筋肉隆々・八十チカラの持ち主)が松浦郡の語元であり、後年の「住吉水軍」の祖となった人物でした!
…
その【松の君】の水軍(神功皇后の軍隊が新羅討伐から帰還した地に建立された神社/現在の建立地は移転後の場所)が、後に【木起神社】と言う~!
…


2024年05月10日
「シロ=城」(稲城)の語元!
日本の国語「ヤマト言葉」。そのルーツはギリシアのイオニア式に因る文字配列順である事を証明する文言が、唯一『ほつまつたゑ』(秀眞伝・35章)文書に取り込まれています。
…
因みに、倭語(ヤマト言葉)の【キ=シロ】に対す漢字の当て字は「城」となっている。尚、その成り立ちは~「土」と「成」の字であり、土を盛り上げ人を入れて安定させると言う意味とされる。 然し、我が国に於ける倭語「キ=シロ」の語意は、元来(古くは)漢字の城ではなく、敵の攻撃を防ぐ構築物(山や柵)の意、早い話が少なくとも土塁ではなく【柵】(稲藁等の柵/イナキ)の意であった。その初出とされる文言が『ホツマツタヱ』(35章・ヒボコ来たる住まいのアヤ/相撲の語元)文書に記述されています~
…
★『ほつまつたゑ』(人の巻35章・ヒボコ来たる住まいのアヤ)より抜粋~
◆(前文略)~時にサホ彦、イナキ(稲城)成し、固く防ぎて、クダリ(降り)えず、キサキ(后)悲しみ、我れ例ひ、世にあるとても、シム枯れて、何オモシロ(面白)と、ミコ(御子)いだき、イナキに入れば、ミコトノリ(詔)、后と御子を出すべしと、あれどいださず、ヤツナダ(豊城入彦命の子で上毛野君の遠祖)が、火責めに成せば、キサキ先ず、御子いだかせて、城お越え、君に申うさく、兄が罪、逃れん為に、我入れど、共に罪ある、事を知る、例ひマカ(罷)れど、ミメクミ(御恵)お、忘らで後の、定めには、タニハチウシ(サホ姫の義兄弟)の、メ(姫)おもがな、君が許しのある時に、ホノオ(炎)オコ(熾)りて、シロ(城=稲城)崩る、諸人され(更)ば、サホ彦と、后も罷る、ヤツナダが、イサオシホメ(功褒)て、賜う名は、タケヒムケ(猛火向け)彦(後文略)。
…
つまり、【ヤマト言葉】文言文字(AD780年=宝亀11年頃大伴家持が関わって完成した『萬葉集』。その万葉仮名の元典でもある『ほつまつたゑ』を構成する【秀真・文字】(基本48文字)は、イオニア式24文字に合致させて「アワ=天地・歌」と称し、口伝「ゲマトリア教義」(カバラ行儀の初出はサルゴン二世の或る文言数価に始まる)を秘密裏に組み込んだ文言を用い【イナキ=稲柵】と書き表されている。
…
何故かと言えば、その【ア・ワ歌】(天の段24文字・地の段24文字)の第7番目の文字「キ」は、ギリシア文字第7番目「H」(古フェニキア文字の成り立ちもH=柵)に当る。従って、その「H」の字元「柵」(囲いを意味す)に対し倭語「シロ」と造語するを以て、ホツマ文字「アの段第」7番目文字「キ」(H・柵)に対する呼称であるシロを、稲藁で造ったので【イナ・キ】(稲城)と言う~。
…
因みに、我が国の【国学】とは「国語学」(文字の学問)の事であり、それは少なくとも聖徳太子=厩戸皇子時代以降に始まる稗田阿礼の口語体文言文書『古事記』&国書【日本紀】(紀はギと読む/現在は逸書と成っている)に始まる「万葉仮名」に対する学問とされる。つまり早い話が、我が国には国家としての創建ルーツ、及び、その「ヤマト国家の起元」を研究する学問は存在しない(その学問は戦後廃止された)等の事が、『母語としての日本語の歴史』(国学者・小松英雄著)の文中に記述されています。早い話が、我が国には「国家の創建を研究する学問は全く存在しない」と言う事であります~
…


…
因みに、倭語(ヤマト言葉)の【キ=シロ】に対す漢字の当て字は「城」となっている。尚、その成り立ちは~「土」と「成」の字であり、土を盛り上げ人を入れて安定させると言う意味とされる。 然し、我が国に於ける倭語「キ=シロ」の語意は、元来(古くは)漢字の城ではなく、敵の攻撃を防ぐ構築物(山や柵)の意、早い話が少なくとも土塁ではなく【柵】(稲藁等の柵/イナキ)の意であった。その初出とされる文言が『ホツマツタヱ』(35章・ヒボコ来たる住まいのアヤ/相撲の語元)文書に記述されています~
…
★『ほつまつたゑ』(人の巻35章・ヒボコ来たる住まいのアヤ)より抜粋~
◆(前文略)~時にサホ彦、イナキ(稲城)成し、固く防ぎて、クダリ(降り)えず、キサキ(后)悲しみ、我れ例ひ、世にあるとても、シム枯れて、何オモシロ(面白)と、ミコ(御子)いだき、イナキに入れば、ミコトノリ(詔)、后と御子を出すべしと、あれどいださず、ヤツナダ(豊城入彦命の子で上毛野君の遠祖)が、火責めに成せば、キサキ先ず、御子いだかせて、城お越え、君に申うさく、兄が罪、逃れん為に、我入れど、共に罪ある、事を知る、例ひマカ(罷)れど、ミメクミ(御恵)お、忘らで後の、定めには、タニハチウシ(サホ姫の義兄弟)の、メ(姫)おもがな、君が許しのある時に、ホノオ(炎)オコ(熾)りて、シロ(城=稲城)崩る、諸人され(更)ば、サホ彦と、后も罷る、ヤツナダが、イサオシホメ(功褒)て、賜う名は、タケヒムケ(猛火向け)彦(後文略)。
…
つまり、【ヤマト言葉】文言文字(AD780年=宝亀11年頃大伴家持が関わって完成した『萬葉集』。その万葉仮名の元典でもある『ほつまつたゑ』を構成する【秀真・文字】(基本48文字)は、イオニア式24文字に合致させて「アワ=天地・歌」と称し、口伝「ゲマトリア教義」(カバラ行儀の初出はサルゴン二世の或る文言数価に始まる)を秘密裏に組み込んだ文言を用い【イナキ=稲柵】と書き表されている。
…
何故かと言えば、その【ア・ワ歌】(天の段24文字・地の段24文字)の第7番目の文字「キ」は、ギリシア文字第7番目「H」(古フェニキア文字の成り立ちもH=柵)に当る。従って、その「H」の字元「柵」(囲いを意味す)に対し倭語「シロ」と造語するを以て、ホツマ文字「アの段第」7番目文字「キ」(H・柵)に対する呼称であるシロを、稲藁で造ったので【イナ・キ】(稲城)と言う~。
…
因みに、我が国の【国学】とは「国語学」(文字の学問)の事であり、それは少なくとも聖徳太子=厩戸皇子時代以降に始まる稗田阿礼の口語体文言文書『古事記』&国書【日本紀】(紀はギと読む/現在は逸書と成っている)に始まる「万葉仮名」に対する学問とされる。つまり早い話が、我が国には国家としての創建ルーツ、及び、その「ヤマト国家の起元」を研究する学問は存在しない(その学問は戦後廃止された)等の事が、『母語としての日本語の歴史』(国学者・小松英雄著)の文中に記述されています。早い話が、我が国には「国家の創建を研究する学問は全く存在しない」と言う事であります~
…



2024年05月01日
日本全国の度肝を抜くなら【伊万里で決まり】!
◆日本全国の度肝を抜くなら【伊万里で決まり】!
…
伊万里に、「所謂神代文字」(いわゆるジンダイ文字/国語学者の山田 孝雄論)と言われた【神代文字】(物部文字は草書体も在る)が刻まれた遺物が伊万里の楠久に在ったと伊万里の或る人に訊きました。その神代文字が公(オオヤケ)になったのは、隠されていた文字を聖徳太子(八耳王・厩戸皇子)が探し出した事に始まります。そしてその文字を漢字に書き換えたのが『先代旧事本紀大成経』(72巻本/『日本書紀』の底本)です。
…
従って、我が国最古の歴史書とされる『日本書紀』の推古天皇迄は、その【大成経・72巻本】の帝紀、旧事」(古い事柄)を取り込んで書かれています。然し、物部氏族が曽我氏に敗れて秋田に逃れた以降、神代文字は公の場から抹殺(弓削の道鏡の陰謀)されました。だが、佐賀の「潮音道海禅師」(ちょうおんどうかいぜんじ/1628年=寛永5年に佐賀県で生まれ13歳で出家/黄檗宗の僧/肥前小城郡)が、『先代旧事本紀大成経』(72巻本)を出版(偽書ではありません/禁書にされたのは伊勢神宮とのトラブルに起因する)した事に因って、現在に蘇っています。
…
その底本(ジンダイモジ文書)に記載されている「カイジン(海人)ワダツミ」(豊玉姫の父/娘の豊玉姫は山幸彦=彦ホホデミノミコトの妻で初代神武天皇の父方の祖母に当る)が拠点としていた有明海北西部(卑弥呼時代初期=AD185年頃に卑弥呼立つ) から良質の黒曜石の産地【ゐまり】(伊万里市の語元)へ進出し、我が国最初の海軍を創設(卑弥呼の使者を載せた水軍)しました。それが【魏志倭人伝】に記述されている「末廬国」(マツラ国は後に言う松浦郡の語元)の水軍(住吉氏族の祖・島津ウシに始まるシマツ彦とは大国主の子)であった~
…
★【松浦】の初出は、魏志倭人伝(280~297)に記す「末廬国」(末=松が正しい/万葉集873~875でも麻通良=【松浦】と記す)です。
…
その語元は、筑紫(最初は九州全体を指す呼称だった)の「32県」(アガタ)を統括し、有明海北西部(大型甕棺墓時代の吉野ケ里遺跡に関連す/伊万里市からも大型甕棺墓が出土)を居住地としていた「ワダツミ=ハデツミ」(海神/神武天皇の父の父)の娘の豊玉姫を后とする山幸彦(彦ホホデミ尊)が率いた水軍(後に言う住吉水軍の祖)の王【松の君】(波乗り彦=松の木のコブ的筋肉隆々で八十力の持ち主を有す長身者集団を率いていた人物)の呼称に起因します。
…
因みに、【松の君】水軍の伊万里に於ける痕跡は、任那(ミマナとは崇神天皇の御名ミマキ入彦のミマを用い朝鮮半島の角ガアラヒトに賜った国称/敦賀の語元)を助ける為の高句麗との戦(広開土王碑文)を終え帰還した事を記念し、伊万里に神社が建立された事であります。
…
つまり、その史実を記す文書が『伊万里市史』に記載されている「神功皇后さんと木超(オコ)し神社」伝承(牧島地区の歴史伝承)です。因みに、「松の木起し」の語意は、神功皇后紀に記す文言~つまり、《神功皇后9年秋・時皇后親執斧鉞、令三軍曰「金鼓無節・旌旗錯亂、則士卒不整」(カネツヅミ、ワイタメなし=カネをならしてもせつどがなくなり、ハタがサクランしたら、イクサのヒトども=つまり松の君が率いる水軍どもの士気が整わない意/高句麗との戦を前にして士気をたかめろと言う叱咤激励的文言に当る)を示唆する文言に起因します~!!
…
話は変わるが~伊万里(佐賀県)に、「所謂神代文字」(いわゆるジンダイ文字/国語学者の山田 孝雄・論)と言われた【神代文字】(物部文字は草書体も在る)が刻まれた遺物が伊万里の楠久に在ったと伊万里の或る人に訊きました。その神代文字が公(オオヤケ)になったのは、隠されていた文字を聖徳太子(八耳王・厩戸皇子)が河内の枚岡神社と四国のアワミヤ(琴平宮)から探し出した事に始まります。そしてその文字を聖徳太子が漢字に書き換えたのが『先代旧事本紀大成経・72巻本』です。因みに、その本の「旧事・帝紀」等を抜き出し編纂し、AD720=養老四年の時として元正女性天皇に奏上されたのが【日本紀】(ニホンギと読む)です。然し現在は、その【日本紀】は逸書となっています。つまり、養老四年に奏上された【日本紀】の底本が『先代旧事本紀大成経』であった。従って『先代旧事本紀大成経』を偽書と言うのは本末転倒です。
…
現在に言う『日本書紀』の存在は、逸書と成った【日本紀】の下書き文書が「第1回講筵」開催の時にテクスト的に用いられた事に起因する。何故かと言えば、その後の 写本伝承「卜部本」や、「佐々木旧蔵本・田中本・岩崎本」等~10数種の写本伝承文書を明治30年~明治34年に編輯し、経済雑誌社から 国史大系 として 刊行された本の中の1つが、現在の『日本書紀』(国史大系第1巻)だからです。
…
その昔、物部氏が曽我氏に敗れ秋田に逃れた以降、つまり早い話が、神代文字は弓削の道鏡の陰謀(765~767年/孝謙&称徳女帝時代)で焚書にされ、公の場から抹殺されました。だが、佐賀(鍋島)の「潮音道海禅師」(ちょうおんどうかいぜんじ/1628年=寛永5年に佐賀県で生まれ13歳で出家/黄檗宗の僧/肥前小城郡)が、その『先代旧事本紀大成経』(72巻本)を出版(大成経偽書ではありません/禁書にされたのは伊勢神宮とのトラブルに起因)した事に因って現在に蘇っています。
…
『日本書紀』の底本(ジンダイモジ文書=ホツマツタヱ)に記載されている「カイジン」(海人・ワダツミは豊玉姫の父/娘の豊玉姫は山幸彦=彦ホホデミ尊の妻で初代神武天皇の父方の祖母に当る)は、拠点としていた有明海北西部(卑弥呼時代初期=AD185年頃に世襲制の卑弥呼が登場する)から、良質の黒曜石の産地だった【ゐまり】(伊万里市の語元)へ進出し、我が国最初の海軍を創設(卑弥呼の使者を載せた水軍でもある)しました。それが【魏志倭人伝】に記述されている「末廬国」(マツラクニは後に言う松浦郡の語元)の水軍(住吉氏族の祖・島津ウシに始まる/シマツ彦は大国主の子)でした~
…
その、「所謂神代文字」(イワユルジンダイ文字/山田 孝雄・論)で書かれた本が『秀真伝』(ホツマツタヱ)と題し、戦後(第二次世界大戦終了後)の1966年=昭和41年8月に松本善之助氏によって再発見されました。その最初の発見に起因する本、つまり「小笠原長武氏に因る奉呈文書」(画像・右)は、内閣文庫所蔵本(写本時代は1868年・慶応4年〜1921年・大正10年) として既に保存済であった~
…
因みに、その再発見に至った文書は現在、その発見地に近い【中江藤樹(トウジュ)記念館】(滋賀県)に保存されています~
…

…

…

…
伊万里に、「所謂神代文字」(いわゆるジンダイ文字/国語学者の山田 孝雄論)と言われた【神代文字】(物部文字は草書体も在る)が刻まれた遺物が伊万里の楠久に在ったと伊万里の或る人に訊きました。その神代文字が公(オオヤケ)になったのは、隠されていた文字を聖徳太子(八耳王・厩戸皇子)が探し出した事に始まります。そしてその文字を漢字に書き換えたのが『先代旧事本紀大成経』(72巻本/『日本書紀』の底本)です。
…
従って、我が国最古の歴史書とされる『日本書紀』の推古天皇迄は、その【大成経・72巻本】の帝紀、旧事」(古い事柄)を取り込んで書かれています。然し、物部氏族が曽我氏に敗れて秋田に逃れた以降、神代文字は公の場から抹殺(弓削の道鏡の陰謀)されました。だが、佐賀の「潮音道海禅師」(ちょうおんどうかいぜんじ/1628年=寛永5年に佐賀県で生まれ13歳で出家/黄檗宗の僧/肥前小城郡)が、『先代旧事本紀大成経』(72巻本)を出版(偽書ではありません/禁書にされたのは伊勢神宮とのトラブルに起因する)した事に因って、現在に蘇っています。
…
その底本(ジンダイモジ文書)に記載されている「カイジン(海人)ワダツミ」(豊玉姫の父/娘の豊玉姫は山幸彦=彦ホホデミノミコトの妻で初代神武天皇の父方の祖母に当る)が拠点としていた有明海北西部(卑弥呼時代初期=AD185年頃に卑弥呼立つ) から良質の黒曜石の産地【ゐまり】(伊万里市の語元)へ進出し、我が国最初の海軍を創設(卑弥呼の使者を載せた水軍)しました。それが【魏志倭人伝】に記述されている「末廬国」(マツラ国は後に言う松浦郡の語元)の水軍(住吉氏族の祖・島津ウシに始まるシマツ彦とは大国主の子)であった~
…
★【松浦】の初出は、魏志倭人伝(280~297)に記す「末廬国」(末=松が正しい/万葉集873~875でも麻通良=【松浦】と記す)です。
…
その語元は、筑紫(最初は九州全体を指す呼称だった)の「32県」(アガタ)を統括し、有明海北西部(大型甕棺墓時代の吉野ケ里遺跡に関連す/伊万里市からも大型甕棺墓が出土)を居住地としていた「ワダツミ=ハデツミ」(海神/神武天皇の父の父)の娘の豊玉姫を后とする山幸彦(彦ホホデミ尊)が率いた水軍(後に言う住吉水軍の祖)の王【松の君】(波乗り彦=松の木のコブ的筋肉隆々で八十力の持ち主を有す長身者集団を率いていた人物)の呼称に起因します。
…
因みに、【松の君】水軍の伊万里に於ける痕跡は、任那(ミマナとは崇神天皇の御名ミマキ入彦のミマを用い朝鮮半島の角ガアラヒトに賜った国称/敦賀の語元)を助ける為の高句麗との戦(広開土王碑文)を終え帰還した事を記念し、伊万里に神社が建立された事であります。
…
つまり、その史実を記す文書が『伊万里市史』に記載されている「神功皇后さんと木超(オコ)し神社」伝承(牧島地区の歴史伝承)です。因みに、「松の木起し」の語意は、神功皇后紀に記す文言~つまり、《神功皇后9年秋・時皇后親執斧鉞、令三軍曰「金鼓無節・旌旗錯亂、則士卒不整」(カネツヅミ、ワイタメなし=カネをならしてもせつどがなくなり、ハタがサクランしたら、イクサのヒトども=つまり松の君が率いる水軍どもの士気が整わない意/高句麗との戦を前にして士気をたかめろと言う叱咤激励的文言に当る)を示唆する文言に起因します~!!
…
話は変わるが~伊万里(佐賀県)に、「所謂神代文字」(いわゆるジンダイ文字/国語学者の山田 孝雄・論)と言われた【神代文字】(物部文字は草書体も在る)が刻まれた遺物が伊万里の楠久に在ったと伊万里の或る人に訊きました。その神代文字が公(オオヤケ)になったのは、隠されていた文字を聖徳太子(八耳王・厩戸皇子)が河内の枚岡神社と四国のアワミヤ(琴平宮)から探し出した事に始まります。そしてその文字を聖徳太子が漢字に書き換えたのが『先代旧事本紀大成経・72巻本』です。因みに、その本の「旧事・帝紀」等を抜き出し編纂し、AD720=養老四年の時として元正女性天皇に奏上されたのが【日本紀】(ニホンギと読む)です。然し現在は、その【日本紀】は逸書となっています。つまり、養老四年に奏上された【日本紀】の底本が『先代旧事本紀大成経』であった。従って『先代旧事本紀大成経』を偽書と言うのは本末転倒です。
…
現在に言う『日本書紀』の存在は、逸書と成った【日本紀】の下書き文書が「第1回講筵」開催の時にテクスト的に用いられた事に起因する。何故かと言えば、その後の 写本伝承「卜部本」や、「佐々木旧蔵本・田中本・岩崎本」等~10数種の写本伝承文書を明治30年~明治34年に編輯し、経済雑誌社から 国史大系 として 刊行された本の中の1つが、現在の『日本書紀』(国史大系第1巻)だからです。
…
その昔、物部氏が曽我氏に敗れ秋田に逃れた以降、つまり早い話が、神代文字は弓削の道鏡の陰謀(765~767年/孝謙&称徳女帝時代)で焚書にされ、公の場から抹殺されました。だが、佐賀(鍋島)の「潮音道海禅師」(ちょうおんどうかいぜんじ/1628年=寛永5年に佐賀県で生まれ13歳で出家/黄檗宗の僧/肥前小城郡)が、その『先代旧事本紀大成経』(72巻本)を出版(大成経偽書ではありません/禁書にされたのは伊勢神宮とのトラブルに起因)した事に因って現在に蘇っています。
…
『日本書紀』の底本(ジンダイモジ文書=ホツマツタヱ)に記載されている「カイジン」(海人・ワダツミは豊玉姫の父/娘の豊玉姫は山幸彦=彦ホホデミ尊の妻で初代神武天皇の父方の祖母に当る)は、拠点としていた有明海北西部(卑弥呼時代初期=AD185年頃に世襲制の卑弥呼が登場する)から、良質の黒曜石の産地だった【ゐまり】(伊万里市の語元)へ進出し、我が国最初の海軍を創設(卑弥呼の使者を載せた水軍でもある)しました。それが【魏志倭人伝】に記述されている「末廬国」(マツラクニは後に言う松浦郡の語元)の水軍(住吉氏族の祖・島津ウシに始まる/シマツ彦は大国主の子)でした~
…
その、「所謂神代文字」(イワユルジンダイ文字/山田 孝雄・論)で書かれた本が『秀真伝』(ホツマツタヱ)と題し、戦後(第二次世界大戦終了後)の1966年=昭和41年8月に松本善之助氏によって再発見されました。その最初の発見に起因する本、つまり「小笠原長武氏に因る奉呈文書」(画像・右)は、内閣文庫所蔵本(写本時代は1868年・慶応4年〜1921年・大正10年) として既に保存済であった~
…
因みに、その再発見に至った文書は現在、その発見地に近い【中江藤樹(トウジュ)記念館】(滋賀県)に保存されています~
…

…

…

2024年04月28日
佐賀の語元「賢姫」とはユダヤの初代国王ダビデに関連する人物だった!
◆『肥前風土記』の逸文に記す【ヨト姫】(ヨトヒメ)が佐賀県の語元と成った【サカシヒメ】(賢姫)であった。因みに、別名「ユタヒメ」(豊姫)とは、「豊かな国」の意とする文言に起因する。つまり、ヨト姫の【ヨト】とはイスラエル初代国王ダビデを示唆する文言である。その意味する処は、山幸彦が失った釣り針が、有明海北西部に位置す処の鯛の口から発見(ホツマツタヱ25章 https://gejirin.com/hotuma25.html )された。
…
つまり、鯛の三ツ山鱗を上下に反せばダビデ紋「六芒星」の形状と成る。その【ダビデ】に対する数秘術(カバラのゲマトリリア数価は14=トヨの語元数価)数価【14】(4+6+4=14)を「トヨ」と言い、失った釣り針を探し出した女性に対し、「14=トヨ」を逆さに読んで【ヨトヒメ】と言う名前が与えられた。早い話が~釣り針を探し出した女性「アカメ=赤女」(有明海北西部を拠点としていた王で豊玉姫の父に仕えていた女性)は、「海人ハデツミ王」から「ヨト姫」と言う名前が与えられた。その呼称が後に【賢姫】(ダビデの数価を知っていた意)と呼ばれた由縁である。
…
佐賀県の語元は、『肥前風土記』 (元明女性天皇が和銅6年=713年に諸国に命じ作製させた文書)の逸文(欽明25年11月、肥前国の佐嘉郡に與止姫神=淀姫とも言う)に、「與止(ヨト)姫神」 あり~。と記されていて、その女性が【サカシ姫】(賢姫)であり、肥前国の佐賀の語元であった。
…
その「與止(ヨト)姫神」が鎮座された処の地名(肥前国の佐嘉郡=佐賀県の語元)が、現在に言う佐賀県の語元(黎明の語意を有す語源の意ではない)である。つまり、その語元に関連付けられた「ユタ(豊)姫」とは、ユダヤの初代国王ダビデ(紀元前1040年~紀元前961年)に関連付けられた呼称であり、そのルーツを引く人物だったから「ヨト姫」と命名されたのであった。その呼称の命名の経緯は、彦ホホデミ尊の妻となったトヨ玉姫に起因する。つまり、その物語は『日本神話』に記されている処の「海幸&山幸彦」であるが、それは史実に基づく物語でもあった。何故か言えば、山幸彦が無くした釣り針の発見地は九州有明海の干満差(最大約6メートル程で日本一とされる)に関連付けられた~「ウテナ=台の館の王ハテ祇の持ち物」。つまり【ハテの神風の珠】(筑紫の海神ワタ祇=台の館のハテ王が贈った干満を操る美しい珠/ホツマ25章)をモチーフとして構成されているからである。
…
その物語に因ると~「鯛はウオ(魚)君、御食の物、シルシ(印・標)はウロコ、三ツに山、ウツシ(写)て反す、ミツ山の、鯛は此れ也、口はイム、アカメ(赤女)お誉めて、ヨト姫と名前を賜る」(ホツマ25章)。」~等と記されている。然し、此の話は『日本書紀』と『古事記」の編纂時に削除されています。
…
つまり~鯛の三ツ山鱗を逆さまに上下写し反せば「△&▽の合成形」となる。その意味する処は~【六芒星】(✡)の形状であり、ダビデ紋を意味します。つまり、「ヨト姫」(與止姫)の「ヨト」を逆さに読めば「トヨ」となる。その「トヨ」の文言が「豊受カミ」の語元となりました。早い話が、『日本神話』、及び、【ヤマト(日本)国家創建史】(ホツマツタヱ文書)の作成に当っては、【メビウスの帯・輪】的内容を駆使した堂々巡り的に構成し作成されている。
…
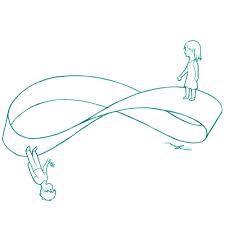
…

…
…
つまり、鯛の三ツ山鱗を上下に反せばダビデ紋「六芒星」の形状と成る。その【ダビデ】に対する数秘術(カバラのゲマトリリア数価は14=トヨの語元数価)数価【14】(4+6+4=14)を「トヨ」と言い、失った釣り針を探し出した女性に対し、「14=トヨ」を逆さに読んで【ヨトヒメ】と言う名前が与えられた。早い話が~釣り針を探し出した女性「アカメ=赤女」(有明海北西部を拠点としていた王で豊玉姫の父に仕えていた女性)は、「海人ハデツミ王」から「ヨト姫」と言う名前が与えられた。その呼称が後に【賢姫】(ダビデの数価を知っていた意)と呼ばれた由縁である。
…
佐賀県の語元は、『肥前風土記』 (元明女性天皇が和銅6年=713年に諸国に命じ作製させた文書)の逸文(欽明25年11月、肥前国の佐嘉郡に與止姫神=淀姫とも言う)に、「與止(ヨト)姫神」 あり~。と記されていて、その女性が【サカシ姫】(賢姫)であり、肥前国の佐賀の語元であった。
…
その「與止(ヨト)姫神」が鎮座された処の地名(肥前国の佐嘉郡=佐賀県の語元)が、現在に言う佐賀県の語元(黎明の語意を有す語源の意ではない)である。つまり、その語元に関連付けられた「ユタ(豊)姫」とは、ユダヤの初代国王ダビデ(紀元前1040年~紀元前961年)に関連付けられた呼称であり、そのルーツを引く人物だったから「ヨト姫」と命名されたのであった。その呼称の命名の経緯は、彦ホホデミ尊の妻となったトヨ玉姫に起因する。つまり、その物語は『日本神話』に記されている処の「海幸&山幸彦」であるが、それは史実に基づく物語でもあった。何故か言えば、山幸彦が無くした釣り針の発見地は九州有明海の干満差(最大約6メートル程で日本一とされる)に関連付けられた~「ウテナ=台の館の王ハテ祇の持ち物」。つまり【ハテの神風の珠】(筑紫の海神ワタ祇=台の館のハテ王が贈った干満を操る美しい珠/ホツマ25章)をモチーフとして構成されているからである。
…
その物語に因ると~「鯛はウオ(魚)君、御食の物、シルシ(印・標)はウロコ、三ツに山、ウツシ(写)て反す、ミツ山の、鯛は此れ也、口はイム、アカメ(赤女)お誉めて、ヨト姫と名前を賜る」(ホツマ25章)。」~等と記されている。然し、此の話は『日本書紀』と『古事記」の編纂時に削除されています。
…
つまり~鯛の三ツ山鱗を逆さまに上下写し反せば「△&▽の合成形」となる。その意味する処は~【六芒星】(✡)の形状であり、ダビデ紋を意味します。つまり、「ヨト姫」(與止姫)の「ヨト」を逆さに読めば「トヨ」となる。その「トヨ」の文言が「豊受カミ」の語元となりました。早い話が、『日本神話』、及び、【ヤマト(日本)国家創建史】(ホツマツタヱ文書)の作成に当っては、【メビウスの帯・輪】的内容を駆使した堂々巡り的に構成し作成されている。
…
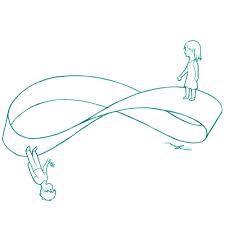
…

…
2024年04月19日
ヤマト言葉ヒフミヨ物部鎮魂神事~「1文字・数価単語」の設定方式


『ホツマツタヱ』~その「アワ歌・アイウエオ」の記号文字は、ユークリッドの『原論』(ギリシア語ストイケイアの著者=エウクレイデスはプトレマイオス1世治世下のアレクサンドリアで活動していた)内容に起因します。ちなみに、その当時はギリシア語訳聖書(72巻本)が作成された時代に当ります~
…
その母音記号文字「〇・冂・△・.弓・口(ア.イ.ウ.エ.オ)は、プラトン多面体(5種類~火.△/土=地.▢/水.◇)を用い、「空気=空」の記号は、【〇】(空は円形に近い正12面体&正20面体に関連する)の形状を取り込んだ。そして、その子音記号(・.H/I,H/Y.H)は、Godヤハウェ(口にすべからずカミの御名の意/出エジプト記20・1~ 7)を言い表す文言の省略文字、即ち【聖4文字=IHVH&YHVH】、その最初の2文字(・.H/I,H/Y.H)を用いて設定する。そして尚、Godを意味す「初めと終り」の意とする「AとΤ=十」字を取り込み設定(・/I/II/T/Y)されました。因みに、最初の子音の点記号【・】は、ヘブ文字のヨッド(yod・ iod・ jod/ヨッドはAと交換出来た)の意です。尚、子音記号最後の菱形【◇】は、「天と地」の意の【地】の形状を意味します。
…
従って、ホツマ【アワ(天地)歌】の文字配列は、ホツマ文字の母音と子音配列順をギリシアのイオニア式文字配列順方式に合致させて「口伝教義」ゲマトリア数価(数価合計で意味を解す数秘術)の使用を容易にする為に並べ変えられました。そして、ヤマト言葉に因る「1文字数価単語」(天忍穗耳尊系物部氏族に伝承された/ヒフミ鎮魂歌神事)が造語されました。
◆【1文字・数価言語】~「ヒ8+フ13+ミ10+ヨ5+ヰ19+ム15+ナ4+ヤ23+コ22+ト2+モ1+チ16+ロ3=141」。+ト迄数えて(55+141=196)震え唯~「フル」(フ91+ル78=169+ト迄の合計196=1年循環法則数価365)の事ぞとミコトノリ(詔/ホツマ第20章)~。つまり「既に罷るも蘇る」とは、1年循環(春夏秋冬)法則数価365に基づき、春になれば「枯れた植物は蘇る」と言う事を示唆する神事(当時は立春正月だったから大晦日頃の神事とされていた?)であった。
…
2024年03月20日
日本語「ハル.ナツ.アキ.フユ」(春夏秋冬)の造語者は大祭司【ΙΑΩ=八尾のアラヒト】!
◆「IAΩ=ヤオ」(1947年発見の死海文書の断片文字が初出/八尾市の語元文字)の語元に始まる【日本建国・創建史】!!
…
◆「IAΩ=ヤオ」(1947年発見の死海文書の断片文字が初出/八尾市の語元文字)の語元に始まる【日本建国・創建史】!!
日本語の季節文言~「ハ3+ル12+ナ4+ツ11+ア1+キ7+フ13+ユ14/計65」(春夏秋冬/アドナイ・メシア=ADNI数価65)を造語したのは、大祭司【ヤオのアラヒト」でした。
…
今日、閏年2024年(令和6年)3月20日水曜は【春分の日】(秋分から春分迄は約197日目で次の秋分迄は約186日目で1年365日となるが今年は閏年なので187日目にあたる)。その、1年循環法則(年中行事の設定)が我が【日本建国創建思想】(AD1世紀~4世紀頃迄の時代の物語)の根元であった~
…
つまり、秋分から春分迄は約「179日」。その【数価179】を語元として我が国の季節呼称「アキ=秋」が造語されました。その「アキ」の造語の経緯は神代の時として、ホノアカリテル彦(瓊瓊杵尊の兄)が東北のクニトコタチの国(現在の茨城県地域)から奈良の斑鳩の里に天降御座するに先立って、ミコトノリ(詔)が発せられた~
★マウラ(占い者)お召して、ウラ(占い)問えば、マウラフトマニ(真占太占)、アキニ(秘儀数価179は春分の日を示唆する文言)取る、今春(春分の日)なれば、西の空、民疲れ無し、ヨシ(秘儀数価186は春分から秋分の日迄の数価)良しと、ミコト(ミコトノリ・詔)定まる(179+186=1年循環法則数価365/ホツマツタヱ・20章)~
…
つまり、それが我が国の建国思想(ホツマ=ヤマトとは世界で最初の1日&1年の朝日が昇る地域の意)文言であった。それを要約した文言が~
★卅有一年(西暦31年はイエスキリストが十字架刑に処された年に当る)夏四月乙酉朔、皇輿巡幸。因登腋上嗛間丘而廻望國狀曰「姸哉乎、國之獲矣。姸哉、此云鞅奈珥夜。雖內木錦之眞迮國、猶如蜻蛉之臀呫焉(トンボがツガル形状/二つの物が一組みになる意)」由是、始有秋津洲之號(ヤマトの国号)也。従って~「昔、伊弉諾尊目曰、此国曰、日本者浦安国、細戈千足国、磯輪上秀真国(袍図莽句爾=ホツマクニとはヤマトクニと同義語)」~と『日本書紀』の神武天皇31年条に記載されています。
…
因みにみ、その筋書きを創ったのは、現在の八尾市竹淵(タコチ)地域を居住地としていた大祭司「ヤオ(ΙΑΩ)のアラヒト」(世襲呼称)でした~
…~「ハ3+ル12+ナ4+ツ11+ア1+キ7+フ13+ユ14/計65」(春夏秋冬/アドナイ・メシア=ADNI数価65)を造語したのは、大祭司【ΙΑΩ=八尾のアラヒト」でした。
…
今日、閏年2024年(令和6年)3月20日水曜は【春分の日】(秋分から春分迄は約197日目で次の秋分迄は約186日目で1年365日となるが今年は閏年なので187日目にあたる)。その、1年循環法則(年中行事の設定)が我が【日本建国創建思想】(AD1世紀~4世紀頃迄の時代の物語)の根元であった~
…
秋分から春分迄は約「179日」。その【数価179】を語元として我が国の季節呼称「アキ=秋」が造語されました。その「アキ」の造語の経緯は神代の時として、ホノアカリテル彦(瓊瓊杵尊の兄)が東北のクニトコタチの国(現在の茨城県地域)から奈良の斑鳩の里に天降御座するに先立って、ミコトノリ(詔)が発せられた~
…
★マウラ(占い者)お召して、ウラ(占い)問えば、マウラフトマニ(真占太占)、アキニ(秘儀数価179は春分の日を示唆する文言)取る、今春(春分の日)なれば、西の空、民疲れ無し、ヨシ(E15+Σ171=186/秘儀数価186は春分から秋分の日迄の数価)、良しと、ミコト(ミコトノリ・詔)定まる(179+186=1年循環法則数価365/ホツマツタヱ・20章)~
…
つまり、それが我がホツマ=ヤマ国の【建国思想】(ホツマ=ヤマトとは世界で最初の1日&1年の朝日が昇る地域の意)文言であった。その文言れを★要約した文言が~
…
★卅有一年(西暦31年はイエスキリストが十字架刑に処された年)夏四月乙酉朔、皇輿巡幸。因登腋上嗛間丘而廻望國狀曰「姸哉乎、國之獲矣」。姸哉、此云鞅奈珥夜。雖內木錦之眞迮國、猶如蜻蛉之臀呫焉(トンボがツガル形状/二つの物が一組みになる意)」由是、始有秋津洲之號(ヤマトの国号)也。従って~「昔、伊弉諾尊目曰、此国曰、日本者浦安国、細戈千足国、磯輪上秀真国(袍図莽句爾=ホツマクニとはヤマトクニと同義語)」~と、『日本書紀』の神武天皇31年条に記載されています。
…
因みにみ、そのカミ代の筋書きを創ったのは、現在の八尾市竹淵(タコチ)地域を居住地としていた大祭司「ヤオ(ΙΑΩ)のアラヒト」(世襲呼称)でした~
…
…
◆「IAΩ=ヤオ」(1947年発見の死海文書の断片文字が初出/八尾市の語元文字)の語元に始まる【日本建国・創建史】!!
日本語の季節文言~「ハ3+ル12+ナ4+ツ11+ア1+キ7+フ13+ユ14/計65」(春夏秋冬/アドナイ・メシア=ADNI数価65)を造語したのは、大祭司【ヤオのアラヒト」でした。
…
今日、閏年2024年(令和6年)3月20日水曜は【春分の日】(秋分から春分迄は約197日目で次の秋分迄は約186日目で1年365日となるが今年は閏年なので187日目にあたる)。その、1年循環法則(年中行事の設定)が我が【日本建国創建思想】(AD1世紀~4世紀頃迄の時代の物語)の根元であった~
…
つまり、秋分から春分迄は約「179日」。その【数価179】を語元として我が国の季節呼称「アキ=秋」が造語されました。その「アキ」の造語の経緯は神代の時として、ホノアカリテル彦(瓊瓊杵尊の兄)が東北のクニトコタチの国(現在の茨城県地域)から奈良の斑鳩の里に天降御座するに先立って、ミコトノリ(詔)が発せられた~
★マウラ(占い者)お召して、ウラ(占い)問えば、マウラフトマニ(真占太占)、アキニ(秘儀数価179は春分の日を示唆する文言)取る、今春(春分の日)なれば、西の空、民疲れ無し、ヨシ(秘儀数価186は春分から秋分の日迄の数価)良しと、ミコト(ミコトノリ・詔)定まる(179+186=1年循環法則数価365/ホツマツタヱ・20章)~
…
つまり、それが我が国の建国思想(ホツマ=ヤマトとは世界で最初の1日&1年の朝日が昇る地域の意)文言であった。それを要約した文言が~
★卅有一年(西暦31年はイエスキリストが十字架刑に処された年に当る)夏四月乙酉朔、皇輿巡幸。因登腋上嗛間丘而廻望國狀曰「姸哉乎、國之獲矣。姸哉、此云鞅奈珥夜。雖內木錦之眞迮國、猶如蜻蛉之臀呫焉(トンボがツガル形状/二つの物が一組みになる意)」由是、始有秋津洲之號(ヤマトの国号)也。従って~「昔、伊弉諾尊目曰、此国曰、日本者浦安国、細戈千足国、磯輪上秀真国(袍図莽句爾=ホツマクニとはヤマトクニと同義語)」~と『日本書紀』の神武天皇31年条に記載されています。
…
因みにみ、その筋書きを創ったのは、現在の八尾市竹淵(タコチ)地域を居住地としていた大祭司「ヤオ(ΙΑΩ)のアラヒト」(世襲呼称)でした~
…~「ハ3+ル12+ナ4+ツ11+ア1+キ7+フ13+ユ14/計65」(春夏秋冬/アドナイ・メシア=ADNI数価65)を造語したのは、大祭司【ΙΑΩ=八尾のアラヒト」でした。
…
今日、閏年2024年(令和6年)3月20日水曜は【春分の日】(秋分から春分迄は約197日目で次の秋分迄は約186日目で1年365日となるが今年は閏年なので187日目にあたる)。その、1年循環法則(年中行事の設定)が我が【日本建国創建思想】(AD1世紀~4世紀頃迄の時代の物語)の根元であった~
…
秋分から春分迄は約「179日」。その【数価179】を語元として我が国の季節呼称「アキ=秋」が造語されました。その「アキ」の造語の経緯は神代の時として、ホノアカリテル彦(瓊瓊杵尊の兄)が東北のクニトコタチの国(現在の茨城県地域)から奈良の斑鳩の里に天降御座するに先立って、ミコトノリ(詔)が発せられた~
…
★マウラ(占い者)お召して、ウラ(占い)問えば、マウラフトマニ(真占太占)、アキニ(秘儀数価179は春分の日を示唆する文言)取る、今春(春分の日)なれば、西の空、民疲れ無し、ヨシ(E15+Σ171=186/秘儀数価186は春分から秋分の日迄の数価)、良しと、ミコト(ミコトノリ・詔)定まる(179+186=1年循環法則数価365/ホツマツタヱ・20章)~
…
つまり、それが我がホツマ=ヤマ国の【建国思想】(ホツマ=ヤマトとは世界で最初の1日&1年の朝日が昇る地域の意)文言であった。その文言れを★要約した文言が~
…
★卅有一年(西暦31年はイエスキリストが十字架刑に処された年)夏四月乙酉朔、皇輿巡幸。因登腋上嗛間丘而廻望國狀曰「姸哉乎、國之獲矣」。姸哉、此云鞅奈珥夜。雖內木錦之眞迮國、猶如蜻蛉之臀呫焉(トンボがツガル形状/二つの物が一組みになる意)」由是、始有秋津洲之號(ヤマトの国号)也。従って~「昔、伊弉諾尊目曰、此国曰、日本者浦安国、細戈千足国、磯輪上秀真国(袍図莽句爾=ホツマクニとはヤマトクニと同義語)」~と、『日本書紀』の神武天皇31年条に記載されています。
…
因みにみ、そのカミ代の筋書きを創ったのは、現在の八尾市竹淵(タコチ)地域を居住地としていた大祭司「ヤオ(ΙΑΩ)のアラヒト」(世襲呼称)でした~
…

2024年03月14日
「日本国家・創建年」は【荒神谷遺跡】(銅剣358本出土)に関連する!

…
【追記】~★日本人の聖書として書かれた『秀真伝』(逸書「日本紀」⇨現存『日本書紀』の底本)!!
…
現存『日本書紀』巻頭文の日本開闢物語(劈頭=ヘキトウ聖句の漢字130字文言)は、『旧約聖書』創世記の劈頭聖句(モーセ五書・創世記の劈頭文言)の焼き直し版である。その証拠は「ミコト」の語元(創世記のアッカド語BRASIT⇨ベラシト秘儀数価3910⇨ミコト・命=尊)です。つまり早い話が、日本語訳としての秀眞伝(ホツマツタヱ)の姉妹書とされる三笠文(ミカサフミ)、その「タカマ成るアヤ」(6章)の文面の編集文言と考えられます。
…
ミコトの語元ルーツは、旧約聖書の創世記(BRASIT=ベラシトとは始めに~の意)のアッカド語BRASIT数価3910(ミコト・命・尊)であり、それを倭語(ヤマト言葉)に変換するに当たっては「ミコ39×ト10=390」として、それはユダヤ民族の罪咎に対する悔い改め期間年数(エゼキエル書4・4~5)である。その証拠と成るのが加茂岩倉遺跡(島根県※雲南市)出土の「銅鐸39個」。又、その近くの荒神谷遺跡(島根県出雲市)出土の「銅剣358本」です。つまり、その数価「39」と「358」が意味する処は、創世記49・9~10に記す~「イェバ・シロー文言フレーズ数価358」(メシアが来るであろうの意)と言う最初の預言であり、又、「39」は、ヤマト国家の創建に関連します~
…
その銅鐸39個と銅剣358本が埋められた事を記す文言がホツマツタヱ(ホツマ34章・60年条)に記載されています。因みに、その始まりは~孝霊天皇から賜った「玉川・カン宝フミ」(武田の祖タケトメ=ハラオ君瓊瓊杵尊の子でホノアカリ。その長男で梅ヒト(三男が山幸彦ホホデミ尊)の長男ニギハヤヒ国照の弟タケヒテルが出雲の国に納めた文書に関連する(ホツマ32章参照の事)。
…
★五七調歌~「八雲立つ、出雲健(タケル)が、ハケル(佩ける)太刀、ツヅラ(葛籠)サワ(沢山)巻き、憐れサヒ(眞刀)無し」(ホツマ34章60年条)。
★「タマモ(魂も)シツ(鎮)、出雲マツラハ、マクサマシ、カヨ代オシフリ、ネミカガミ(寝身・鏡/景初三年銘入・三角縁神獣鏡)、ミソコ(39)宝の、ミカラヌシ(身空主)、谷身括り身(荒神谷遺跡出土の銅剣358本は括られていた/島根県出雲市斐川町神庭から出土)、タマシツカ(魂静か)、ウマシ御カミは、ミカラヌシ(身空主)ヤモ」。
※卑弥呼の鏡とされる【三角縁神獣鏡】(景初三年銘入鏡)も、銅鐸が一括して39個出土した島根県雲南市「神原神社古墳」から出土している。
…
因みに現存『日本書紀』の崇神天皇60年条の漢字訳は、意味が通っていません(チンプンカンプン)~
…
「ミソコ(39)宝」の数価【39】の出自は、古典期ギリシア27文字配列順数価を用いた「ミK11+ソΔ4+コΧ24=39」文言数価である。つまり、それを創世記のアッカド語(アラム語は紀元前アッシリア&新バビロニア王国の公用語)による文言BRASIT(ベラシト)の秘儀数価「3910」(ミコトの語元ルーツ)に関連付けるを以って、エゼキエルが定めた罪咎に対する悔い改め期間年数価390」(エゼキエル書4・4~5)を示唆すると共に、ミコト(39×10=390)の語元と定義し、設定しました。
…
その解読に至ったのは、1948年4月12日付ロンドンタイムス紙の二十世紀最大の考古学的発見(羊皮紙巻物=死海文書)と言うニュースによって、それ迄は歴史の闇に閉ざされていたクムラン秘儀教義宗団(ダマスコ契約宗団はエゼキエルが定めた悔い改め390年を全うした宗団であった)の存在が初めてあかるみと成った事に起因します。つまり、クムラン集会所遺跡の発掘調査率いたフランスの考古学者でカトリック教会の神父でもあるロラン・ドゥ・ヴォー氏によると、紀元前31年にクムラン地域をも襲った大地震で集会所も破壊された。そしてそれ以後、その秘儀教義宗団の行方は不明とされています~【追記】以上~
…
【ヤマト言葉】(国語)の始まりは、伊万里の語元数価358に起因する。そしてその秘儀数価【358】は、「日本国家・創建年」に関連する【荒神谷遺跡】から出土した「銅剣358本」にも関連する!
…
今日は「2024年2月11日・建国記念日」。その 神武天皇の即位元年を紀元前「660年」とするのは間違っています。つまり、国家としての実質的成立年は「幻の西暦351年」に当る崇神天皇12年条(日本書紀)に記すミコトノリ(詔)。即ち~「肇(ハツ)国知らすミマキ(崇神天皇)の代」と発せられた文言に起因します。
…
その詔の年を以って新たにヤマトの歴年史は再設定されました。その再設定方式は、【太神宮諸雑事記第一】に記す雄略天皇21年(AD477年=伊勢皇大神宮建立年)から484年過去に遡った紀元前7年の時と記すが、その原点は崇神天皇12年(AD351年)から過去に伊万里の語元数価年「358」(創世記49・9~10・メシア=シロが来る意の文言数価/ゐ.T190+ま.E15+り.R153=358)遡った紀元前7の時として設定された「長髄彦討伐6年戦争」(神武東征はハルマゲドンの模倣戦)完了後に当たる「幻の西暦1年目・辛酉」(ヘロデ王の第7年=ユダヤ大地震発生年から31年目)が、本当の日本の建国元年に当ります。
…
因みに、その「660」と言うのは、苦戦を強いられ八尾の竹淵(タコチ)地域にタケヒト(神武の幼名)皇軍が陣を退き(八尾市史・竹淵神社縁起参照)、作戦を変更した紀元前3年から「660年後」(垂仁天皇26=紀・在位通歴657年)に、伊勢神宮が建立されたとする数価年に当ります!!
…
2024年02月28日
カミ代文字で書かれた『ホツマツタヱ』(秀真伝)を偽書と言うのは本末転倒です!!
カミ代文字で書かれた『ホツマツタヱ』(秀真伝)を偽書と言うのは本末転倒です!!
…
因みに、日本最古の歴史書とされる現存『日本書紀』とは、養老四年(AD720年)に元正女性天皇に奏上された【日本ギ】(ギ→紀/現在は逸書となっている)の下書き文書が、早速、その翌年に行われた【日本紀】の講筵(講義)にテクスト的に使用(例会は康保2年=965年頃迄ほぼ30年に1回宮中で行われていた)された、その下書き文書を、明治時代に経済雑誌社が編輯し刊行した本。つまり『日本書紀』(ヤマトフミ)とは、【日本紀】(逸書・日本紀)の下書き写本伝承本だった。
…
★~現在の日本の歴史学者や言語学者には学問の自由がなく、学生が【神代文字】に付いて卒論を書こうとしたら止められた!!
…
★~日本の言語学者は【ヤマト言葉】を否定し、「上代語」と言い換え、恬(テン/外のものに心を動かさず落ち着いている状態)として恥じない。然しそれは、言語学者として失格である!!
…
…
つまり、講筵の例会で使用されていた【日本紀】の下書き文書の写本伝承文書(佐々木旧蔵本・田中本・岩崎本)等、多々ある文書が、明治30年(1897年)~明治34年(1901年)に『日本書紀』(ヤマトフミ/黒板勝美・校訂)と題し、尚、他の本を合せた17冊を国史大系として経済雑誌社が刊行した本である。
…
その昔、隠されていた土笥(ハニハコ/カミ代文字文書に因るカミ代の時代~景行天皇迄の春日氏文書【ミカサフミ】を保存していた埴土の箱)。その50笥(箱)を小野妹子が平岡宮(枚岡ではない/神津嶽本宮=平岡表記は『先代旧事本紀大成経・72巻』本に記載/現在地は東大阪市出雲井町7番16号)から。又、秦の河勝も四国の泡(アワ)輪(ノ)宮から三輪氏文書【ホツマツタヱ】をそれぞれ「聖徳太子」(厩戸皇子)が探し出し、両名に命じてカミ代の文字で書かれた文書を持ち帰えらせた。此れを以てカミ代と先史(神武天皇~景行天皇迄/AD1世紀~AD4世紀末頃迄)の事が明るみになる。そして尚、隠されていた【6家】(吾道=アチ・物部・忌部・卜部・出雲・三輪)文書、及び中臣御食子の文書。又、推古女性天皇歴年文書等を合せ、漢字編輯に因る『先代旧事本紀大成経』(72巻本)を聖徳太子が完成させました。後年、その「72巻本」の中の「天皇紀」(帝紀)や「宮廷内物語」(旧辞?)等の文章を底本として取り込み書かれたのが【日本紀】(現在は逸書だが扶桑略記・名文抄にはカミ代の年代部分が取り込まれ保存さている)である。
…
【日本紀】(養老四年=AD720年に元正天皇に奏上)が完成し、元正女性天皇(第44代/元明女性天皇の譲位に因る)に奏上された翌年(AD721年)、早速、宮中で「講筵」(こうえん/講義)が行われた時、【日本紀】の下書き文書がテクスト的に用いられ、その後も【講筵】(例会)は康保2年=965年頃迄ほぼ30年に1回行われていた。つまり早い話が、現存『日本書紀』(黒板勝美・校訂)とは、逸書【日本紀】の下書き文書の編輯本である。従って、現存『日本書紀』に在るはずの系図が抜けているのである。然し、その文書の一部分は「名文抄」(続群書類従書/雑部・巻第886)として、少なくともカミ代の系図に関する暦年(鈴木暦)が、鸕鷀草葺不合尊迄で「179萬2476歳」(『神道五部書・倭姫命世記』とほぼ同じ)として保存されています。
…
【古事記】(フルゴトフミ/口述の文書化)は、歴史書でないので、此処では言及致しません~
…

…

…
…
因みに、日本最古の歴史書とされる現存『日本書紀』とは、養老四年(AD720年)に元正女性天皇に奏上された【日本ギ】(ギ→紀/現在は逸書となっている)の下書き文書が、早速、その翌年に行われた【日本紀】の講筵(講義)にテクスト的に使用(例会は康保2年=965年頃迄ほぼ30年に1回宮中で行われていた)された、その下書き文書を、明治時代に経済雑誌社が編輯し刊行した本。つまり『日本書紀』(ヤマトフミ)とは、【日本紀】(逸書・日本紀)の下書き写本伝承本だった。
…
★~現在の日本の歴史学者や言語学者には学問の自由がなく、学生が【神代文字】に付いて卒論を書こうとしたら止められた!!
…
★~日本の言語学者は【ヤマト言葉】を否定し、「上代語」と言い換え、恬(テン/外のものに心を動かさず落ち着いている状態)として恥じない。然しそれは、言語学者として失格である!!
…
…
つまり、講筵の例会で使用されていた【日本紀】の下書き文書の写本伝承文書(佐々木旧蔵本・田中本・岩崎本)等、多々ある文書が、明治30年(1897年)~明治34年(1901年)に『日本書紀』(ヤマトフミ/黒板勝美・校訂)と題し、尚、他の本を合せた17冊を国史大系として経済雑誌社が刊行した本である。
…
その昔、隠されていた土笥(ハニハコ/カミ代文字文書に因るカミ代の時代~景行天皇迄の春日氏文書【ミカサフミ】を保存していた埴土の箱)。その50笥(箱)を小野妹子が平岡宮(枚岡ではない/神津嶽本宮=平岡表記は『先代旧事本紀大成経・72巻』本に記載/現在地は東大阪市出雲井町7番16号)から。又、秦の河勝も四国の泡(アワ)輪(ノ)宮から三輪氏文書【ホツマツタヱ】をそれぞれ「聖徳太子」(厩戸皇子)が探し出し、両名に命じてカミ代の文字で書かれた文書を持ち帰えらせた。此れを以てカミ代と先史(神武天皇~景行天皇迄/AD1世紀~AD4世紀末頃迄)の事が明るみになる。そして尚、隠されていた【6家】(吾道=アチ・物部・忌部・卜部・出雲・三輪)文書、及び中臣御食子の文書。又、推古女性天皇歴年文書等を合せ、漢字編輯に因る『先代旧事本紀大成経』(72巻本)を聖徳太子が完成させました。後年、その「72巻本」の中の「天皇紀」(帝紀)や「宮廷内物語」(旧辞?)等の文章を底本として取り込み書かれたのが【日本紀】(現在は逸書だが扶桑略記・名文抄にはカミ代の年代部分が取り込まれ保存さている)である。
…
【日本紀】(養老四年=AD720年に元正天皇に奏上)が完成し、元正女性天皇(第44代/元明女性天皇の譲位に因る)に奏上された翌年(AD721年)、早速、宮中で「講筵」(こうえん/講義)が行われた時、【日本紀】の下書き文書がテクスト的に用いられ、その後も【講筵】(例会)は康保2年=965年頃迄ほぼ30年に1回行われていた。つまり早い話が、現存『日本書紀』(黒板勝美・校訂)とは、逸書【日本紀】の下書き文書の編輯本である。従って、現存『日本書紀』に在るはずの系図が抜けているのである。然し、その文書の一部分は「名文抄」(続群書類従書/雑部・巻第886)として、少なくともカミ代の系図に関する暦年(鈴木暦)が、鸕鷀草葺不合尊迄で「179萬2476歳」(『神道五部書・倭姫命世記』とほぼ同じ)として保存されています。
…
【古事記】(フルゴトフミ/口述の文書化)は、歴史書でないので、此処では言及致しません~
…

…

…








